INTERVIEW

Artists #39 山田康平
今月7月29日まで、六本木・タカ・イシイギャラリーにて、山田康平さん個展「Strikethrough」が開催されます。
山田さんはCAF賞2020(https://gendai-art.org/caf_single/caf2020/)で入選、タカ・イシイギャラリーでは初個展となる本展では、新作も含めたキャンバス、紙の作品を展示されます。インタビューでは本展を中心に、現在のご活動についてもお話を伺います。
--この度は個展開催おめでとうございます!個展についていろいろお聞かせください。まずは、開催に至った経緯を教えていただけますか。
山田:僕は大学院は京都造形芸術大学(*現在の名称は京都芸術大学)に在籍していたのですが、タカ・イシイギャラリーのオーナーである石井孝之さんは大学に客員教授として年に数回いらしていました。そのご縁から、講評いただくタイミングで、大学院一年生の時から作品を見ていただいていました。石井さんはどの学生の作品に対してもネガティブな評価はされない方で、よく褒めてくださって、僕も学生の一人として、よく見守ってくださっているんだなと思っていました。二年生の頭くらいに、6号(41 × 31.8cm)くらいの僕の作品を買ってくださったことがありました。その後、僕の大学院の卒業制作作品を見たときに、個展をしませんか、とお話をいただきました。大学院一年生から二年生にかけて、僕の作品がどんどん変わっていったので、作品がさらに進化していく過程も含めて気に入ってくださったのかなと思います。2022年の3月に卒業してからちょっと時間が経ってしまいましたが、調整の上今年の7月に六本木のタカ・イシイギャラリーで開催する運びになりました。

2022年1月に京都岡崎蔦屋書店で開催された個展「線の入り方」の展示の様子
山田:「線」というのは、今も引き続き考えているテーマで、今後も考えを深めていくと思います。ただ今回は、僕の中で線の地続きである「ストローク」に注目しています。僕は作品制作で刷毛をたくさん使うんですが、その刷毛のストロークが気になっています。絵画を描くという印象よりも、色彩によって、色彩の下にある何かを隠したり、覆ったりする意識があるんです。今回の個展は「Strikethrough」とタイトルをつけ、そのストロークについて考えてみる、ということをしています。最近は以前のような分割的な絵というよりも、余白が多い絵を作っています。特に大作だと余白がよく目立つような、そういう意味ではこれまで見せたことがない作品に仕上がっていると思います。
先ほど僕は「線」の地続きと言ったのですが、「線」を考える時に、線はどこまでいったら線なのだろうか、とよく考えます。線みたいなものがだんだんと太くなっていくと、それが「面」になってきて、引いて見ると、巨大な面であっても線になるじゃないですか。絵画作品は、油絵具の特性を生かして筆致をしっかりと残すピーター・ドイグのような作品や、情緒的な画面に仕上げて没入感を作り出すマーク・ロスコのような作品が多いと思いますが、
僕自身は画面をフラットにしたい欲求が強いんです。面と面をぶつけながら空間を見せていきたい空間要素的な意味もあるし、その面によって鑑賞者が弾かれてしまうような画面作りを試みています。一見、画像で見るとフラットだけど、実際に近くで見たらすごく筆致のやりとりが見えて、そこにびっくりして引いてしまう、みたいなことを目指しています。作品に入れそうな気がするけど弾かれてしまう、檻の中で寝ている動物を安心して見ていたら、突然動き出して牙を剥かれたりして、やっぱり動物なんだと思う、みたいな感覚です(笑)。
ほとんどの作家がそうだと思いますが、絵を描いている時は完成が近づくと、自分の意思から絵が離れていくというか、自分の意思とは関係なく、描かされているような感覚に最終的になっていきます。急に自分の絵がそこら辺にあった時に、なんだこれ気持ち悪いな、、みたいな(笑)。面が持っている弾くような印象や、若干の暴力性など、白壁に展示した時に異物感がある絵画に惹かれ、そこを無意識に目指していると考えています。
僕の作品は派手な色彩を多く使っている印象があると思いますが、それも鑑賞者に心地よさを与えたいというより、遠ざけたい気持ちが強いからであると感じます。画面の中に微妙な差し色もあって、そのキレイな差し色に引き寄せられて近寄るけど、目の前にしたら巨大な面に圧倒されて引く、という距離感が今の僕には大事なのかもしれません。もともと僕は以前、「山」や「風景」といった具体的なイメージを描いていたこともありました。今は特定の何かを描いているという意識は全くなく、自分のリズムや色の組み合わせなど絵画的な構成の中で作っていますが、新しい作品もかつてはイメージがあった上で表現が変わっていったんだろうな、というのがわかるような表現のように思い、自分の中でも意識しているところではあります。
--CAF賞2020にご出展いただいた作品は、山を描かれていたんでしょうか。

「Strikethrough」の展示の様子/撮影:高橋 健治
山田:僕の制作スタイルは、あるときを境に急に方向転換をするのではなく、基本的には今までやってきたことの延長、地続きな制作をします。今回の個展は、かなり気合が入っているので、今までやってきたことの集大成的な形で作品を見せられたらいいなと思っています。展示は、個展、グループ展、アートフェアなど、これまでいろいろ参加させていただいていますが、過去の展示で僕の背丈よりも大きい大型作品を出展したことは、実は卒展くらいしかなくて、今回は大型作品も含めてお見せできるので、見応えがあるのではないかと思います。お話しいただいた当初は、今年の2月に個展を開催する方向で進んでいたこともあって、昨年2022年の作品もいくつかあり、直近の作品だけで構成されているわけではありませんが、僕自身、どんな展示が出来上がるのかとても楽しみです。本展ではキャンバスの作品に加えて、「紙の作品」も準備しました。紙というとドローイング作品と思う方もいらっしゃるかもしれないですが、僕の中では「ドローイング作品」という概念はあまりなくて、「紙の作品」とあえて呼んでいます。油彩用アルシュ紙に描くんですが、今までF4号(33.3 × 24.2cm)サイズ程度に描いていたものを、20号(72.7 × 60.6cm)くらいの大きさにも挑戦するようになって、その新しい作品も含めて、たくさんの方にご覧いただきたいです。

《Untitled》2023/紙に油彩/19.1 × 25.1cm/撮影:高橋 健治

《Untitled》2023/紙に油彩/23 × 30.7cm/撮影:高橋 健治
--前回京都での個展「線の入り方」を拝見させていただいた際は、「線について描いている」と伺いましたが、今回は何を描かれていますか。

「CAF賞2020入選作品展覧会」で入選した山田の作品。左から、《ここに在るということ》、《Still life》
山田:実はあれは「ポートレート」を描いています。CAF賞に入選した作品は、150号(227.3 × 181.1cm)と120号(194 × 130.3cm)の大きな絵を出しました。150号は「面」、120号のは「線」で描いていて、2020年当時はドローイングというかイメージのようなものを輪郭で追いかける、という意識をしていました。僕は制作の中で、反復的な画面作りは一番避けたいと思ってます。方法が先に見えてきてしまうような方法論で描きたくないんです。一つの展覧会を作る時は、僕は表現にいくつかバリエーションが欲しいと思っていて、CAF賞の時は線が見えたり面が見えたり、二つの画面を見せていました。今でもすごく覚えているのは、CAF賞の最終審査で保坂健二朗審査員に「120号の絵があることで、150号の絵と表現が解離してしまっているように見える。」とコメントいただいたことです。その言葉を受けて、二枚の絵をどうやって繋げたら良いだろうかと考え、そこから面と線の話を熟考するようになり、CAF賞の審査前と後とで絵がガラッと変わっていきました。僕としてはその二つの作品はどちらも地続きの作品でしたが、イメージを追いかけることを重要視していたために、絵画的な構成が解離してしまっていたということに気が付きました。CAF賞の時は何を描いていても自分の作品になると思っていて、たくさん絵を描きましたが、いっぱい描いていると自分は何を描いているのか収集がつかなくなってきてしまいました。それが保坂さんから指摘された、解離の原因かもしれません。
ただもちろん、たくさん絵を描いたことは無駄にはなっていなくて、描いた経験を多く積んだからこそ、今では筆を動かすだけで、世界の何かの現象とリンクするような感覚があります。一年前にbiscuit galleryで開催した個展では、その刷毛の動かし方が押しては返すような波の動きに近いと感じ、青の色面の余白が抜けていくさまは海を見ているようで、海を描いていたわけではありませんが、現象として海のようなイメージが立ち現れてきました。

2022年5月にbiscuit gallery(東京)で開催された「それを隠すように」の展示の様子
--山田さんは制作もたくさんされますが、展示を見にいかれていたり、展示にご参加も多くされています。そういった経験からも様々な影響を受けているように感じます。
山田:それも多くあります。どんな作家も、誰かの何かの作品の模倣・パクリになってしまうのは良くないと分かっています。でもやっぱり特に絵画だと、意識したわけではないのだけれど誰かの絵に表現が近くなってしまうということは往々にしてあると思います。自分は作品で何を表現するのか、というのを考えたり、見極めたりするには、制作に励んだり思考を深めていくことに加えて、今生きている作家の展示を見るということもとても大事だと思っています。展示だけでなく、政治や社会や世界で、何が起きているのか知ることも大事です。もし世界中に人間が自分一人だけだったら、アートは成り立たないといつも思っています。「アートに力がある」という言葉についても、アートではなく「人間に力がある」のではないかと僕は思っているんです。人間がルールや力の動かし方を作っていて、その流れを知らないと、どれだけ良い表現をしていても独りよがりで思い込みになっていってしまうのかもしれません。一人一人が考えて持っているルールが世界に出た時に、大事な現象や影響をおこしていくのだと思うんです。自分のルールを作るからこそ、周りや世界のルールを知らないといけないなと思っています。他の作家のルールと照らし合わせるような意識で、最近は作家同士のグループ展を企画したりもしました。

2022年10月にYOD TOKYO(東京)で開催された「ぎこちない実感」の展示の様子。山田康平、木津本麗、朝長弘人の三人によるグループ展示
--確かテキストも寄せていらっしゃいましたね。
山田:そうですね、最近は文章も書きます。この展示は僕がキュレーションをした、と言ってしまうとちょっと違うんですが、近い年代の作家三人で企画展示をしました。同じような認識を持っていても作家間でも認識に微妙な差があって、絵画の話をする時とかは大きな主語のようなもので覆われて、細かいところまで差異が確認できないんです。でも一方で、どんどん細かく見る力自体は外からも中からも求められているように思って、その力を身につけるために文章を書いたり、展示を企画したいと思ってやりました。視力を良くしていくような話で、みんなが向いている方向の解像度をあげていきたいんです。いい絵を作る、という話にも通じてくると思います。前回は同じ年代の作家が中心になって行いましたが、今後は亡くなった作家とか、年代が違う作家を招聘して、遠いところで繋がる、ということも面白いのではないかと思っています。
ちょっと話は変わりますが、最近、僕は作品を作る時にプレゼンをしないように作っていることに気がつきました。それはちょっと逃げにも聞こえてしまうかもしれないんですが、僕は作品を「漠然とこうしたい」みたいな欲望はありますが「これをやりたい・表現したい」という明確なゴールは持っていません。ゴールを決めずにスタートして、最終的なゴールはその都度変化していきます。絵を描いていると思わぬアクシデントに遭遇することがあります。自分にとっての絵の上手さは、そのアクシデントをリカバリーできる能力・技術も一つだと思っていて、その過程も含めて表現に現れてくると面白いと思っています。結果的にこうなってしまった、という画面が好ましくて、リカバリーによって紆余曲折する技術に面白さを見出します。
先ほどの質問もそうでしたが、山田さんは何を描いているの、と聞かれることが多いです。僕含めて、多くの作家はプレゼンがあまり上手ではありません。今言ったようなことを、言葉でプレゼンするのはとても難しくて、では言葉以外でどういう形で伝えることができるだろうかと考えた時に、やはり展覧会が一番伝えやすい場だと思ったんです。展覧会の中では僕は作品について多く語れますが、展覧会以外では話しづらくなってしまいます。展示をするタイミングでも見え方は変わってきたりして、時間の経過による変化のズレもポジティブに捉えて説明できます。絵がただの画像ではないという話としても捉えることができます。そんなことがあって、プレゼンとしては良くないんですが、最近は「私は」というよりも「絵画は」のように、自分から離れた主語に置き換えて話す、ということをしています。
数百年前の人が僕の絵を見ても、絶対にわからないと思います。未来の人も、もしかするとわからないかもしれません。ただ何か考えられるようなヒントを残したくて、それが文章だったり、絵の中のルールだったりします。僕の作品は長くずっと見ていると、一貫して辻褄が会うことをしているように感じてもらえると思います。でも同時に、それが最終的にどこにいくかはわかりません。まるで人生そのもののようです(笑)。

「Strikethrough」の展示の様子/撮影:高橋 健治
--山田さんはCAF賞入選時は学生で、現在は拠点も変わり作家業に専念されていますが、卒業前と後とで更なる変化があったと思います。
山田:絵画のことで言えば、美大生になった当初は美術って楽しい!というピュアな気持ちで始めていましたが、やっていくとネガティブなことも当然たくさんありました。スポーツ選手とかだと「選手になる」ために努力すると思いますが、絵描きは「絵描きになる」という概念はないように僕個人は思っています。それはポジティブな意味でもあって、絵を描くということは、ただの画像生成技術者ということでなく、哲学や思想を含み、社会に意見をすることも可能な媒体で、様々な役割を含んでいる作業なんだ、ということに気がついていったんです。そのことに気がついてから、描いている実感の濃度が上がっていき、それをポジティブに捉えることができて、絵はまだ終わっていないな、と思えるようになりました。ここに気がつけたのは、先ほど話したように、かなりの枚数を描いてきた経験があったからこそなのかなと思います。大学院一年生の頃とかは一年に200枚くらい描いていました。その時はほとんど思考していなかったですが、最近はどんな作品を見ても、自分の作品は自分の作品、と思えるようになりました。どこに持っていっても自分の絵になる自信が今はあります。
作品はちょっとうまくなったり、コツを掴んだりすると、もうそこから戻れなくなるだろうと思っています。僕は学部生の頃からたくさんの展示や作品を見てきていますが、その経験も良かったと思っています。表現として強くなっていくと、作品は自分から離れてコントロールができなくなってくるので、絵を制作するということには「見る・確認する作業」もとても大事になってくると思っています。何か一つのやり方に固執してしまったりすると、他のものをどんどん受け入れられなくなってきて、そうすると鑑賞者も作品を受け入れられなくなってくるんです。僕は以前アメリカに行ったことがあるんですが、そこで見た作家は、そういう人がもしかすると多かったように思いました。受け入れられないことで突破する、みたいな印象です。表現を続けていくと、最終的には自分も含めて作家はそうなっていくんだと思うんですが、僕は受け入れられないものが増えてしまうより、少なくとも今は柔軟でありたいと思っています。アートが何かを否定するものになってほしくないんです。確かに、歴史で見たら、アートは否定を繰り返して発展してきました。でも僕は何かを否定して一人突き進むことよりも、この作品も、僕の作品もすごいよね、という、全部一緒に上がっていくことをしたいです。自分一人が上がっていくのではなく、みんなで上がっていきたいんです。僕たちの教授の世代は、ここから現代美術と括られる時代から活躍されている方もいて、そういう方はやっぱり、現代美術そのものの良い悪いの全てを背負っているところがあります。ある意味美術の呪いみたいなものも背負っているんです。では僕たちの世代は一体何を背負うのだろうと考えた時に、背負うものよりも、乗り越えるものであって欲しいと思っています。
僕が初めて絵画っていいなと思ったのは、中国の作家・趙無極(ザオ・ウーキー)の作品を台湾で見た時でした。「あぁ、絵はいいなあ」と心から感動しました。その作品は「書」を抽象絵画におこす、みたいな絵だったんですが、作家が実感を持って描いている作品だなと感じ、絵を描くことに自信があるように感じられたんです。僕は欧米の作家よりもアジアの作家の作品が好きで、良さが心にストンと落ちるのはアジアの作家が多いんです。
--実は山田さんは美術品のコレクターでもあります。収集のきっかけも、「みんなで上がっていく」に関連するのでしょうか。
山田:そうですね、その側面もかなりあります。村上隆さんや奈良美智さんをはじめとする、大御所の美術作家から若手作家まで、僕に限らず作家でありコレクターでもある人はかなりいると思います。特に村上さんは以前横浜美術館でコレクション展示もして、美術品だけでなく骨董も収集しているビッグコレクターです。コレクターの人が持つ、シンプルに「好き」から入っていく気持ちもとても大事だと思うんです。
僕が学部の4年生の頃は美術を否定的な目で見ることが多かったんですが、それではよくないと思って、美術を好きになるために買ったということもありました。どんなことも否定をすることはとても簡単ですが、良さを話すことはとても難しいです。否定することは減らすことでもあります。作家は生み出してプラスを作っていく存在なのに、否定して作っていくのは良くないと思ったんです。それに、美術を好きになっていきながら作った方が制作にも良い影響があるなと思いました。コレクターの間ではよくある話と思いますが、作品を買うことで知ることができる世界というのは作家にもあると思います。僕は全てが完璧というよりも、面白いなとか、いいなと思う要素が一つでもあったらそれを信じて購入しています。
--CAF賞審査員の名和晃平さんの話を聞いているみたいです(笑)。
山田:正直なところ、名和さんのその姿勢の影響はかなりあります。名和さんは京都造形芸術大学では直属の教授ではありませんでしたが、アートのすくい上げ方がポジティブで、否定するのではなく、良いところを探してあてて評価してくださる理想的な先生で先輩です。アートに対して厳しい視線を向けながら、ポジティブな話ができるというのは非常に大事なことだと気付かされます。日本の美術界は、一方向から見たことを深く掘り下げるということは多くあると思うんですが、多角的な視点で評価するということがあまりないように思っています。一方向の角度から見た時に、それがクリティカルな視点だと、全部そちらに持っていかれてしまう危うさがあると思っていて、実はいろいろなところから見ると面白かったりするのに残念だと思うことがありました。先ほど言った、作品の話をする時に主語を大きくして話す、というのも名和さんからの影響です。名和さんのように、もっと様々な視点からアートを捉えられる人が増えたらいいなと思っています。
--最後に今後のご活動についてなど教えてください。
山田:今回のタカ・イシイギャラリーでの個展は、僕にとって一つ大きなステップになると思います。そこから国内だけでなく、海外での展示も展開できるといいです。それから、期間限定ですが、「ZOZOVILLA」から僕の作品がデザインされたラグが発売されています。こういった、展示という形以外での見せ方も、作家活動といい距離を保ちながら、様々に取り組んで行けたらいいなと思っています。

「ZOZOVILLA」が展開するシリーズプロジェクト「THE PACKAGE」の新アイテムとして山田がコラボレーションした「PENDLETON」のブランケット
山田:もう一つ目標として、友達を増やしたいです(笑)。僕は本を読んで知識を広げて深めていくことよりも、フィジカルに人と話したり経験することで深まっていくタイプで、自分の世界や視点を広げていくために、業界や地域など関係ない、もっと様々な人と交流を深めていきたいと思っています。展示も東京だけに集中してやる必要もないと思っていて、日に10〜20人しかこない行きづらい場所であっても、そのうちの一人にとって良い鑑賞体験になるのであれば、それはとても嬉しいことだし、チャレンジしていきたいことだと思っています。
今の作家はSNSなどを通じてあまりにもいろいろなところから視線が多すぎるが故に、「何か早く達成しなきゃいけない」という気持ちが大きくて焦ってしまっている人が多くいます。僕も大学院の時はまさにそうでした。振り返ればその焦りは完全に間違いで、早く達成し過ぎた結果、できなかったこともたくさんあったと思います。その反省をしながら、今後は自分を信じて自分のペースで美術にきちんと向き合う時間を持って整理して、着実に、作家活動を続けたいと思っています。
*トップ展示風景写真:高橋 健治
-
開催概要
タイトル:山田 康平「Strikethrough」
会期:2023年7月1日(土)〜7月29日(土)12:00〜19:00
休廊:日、月、祝日
会場:タカ・イシイギャラリー(東京都港区六本木6-5-24 complex665 3F)
https://www.takaishiigallery.com/jp/archives/29958/
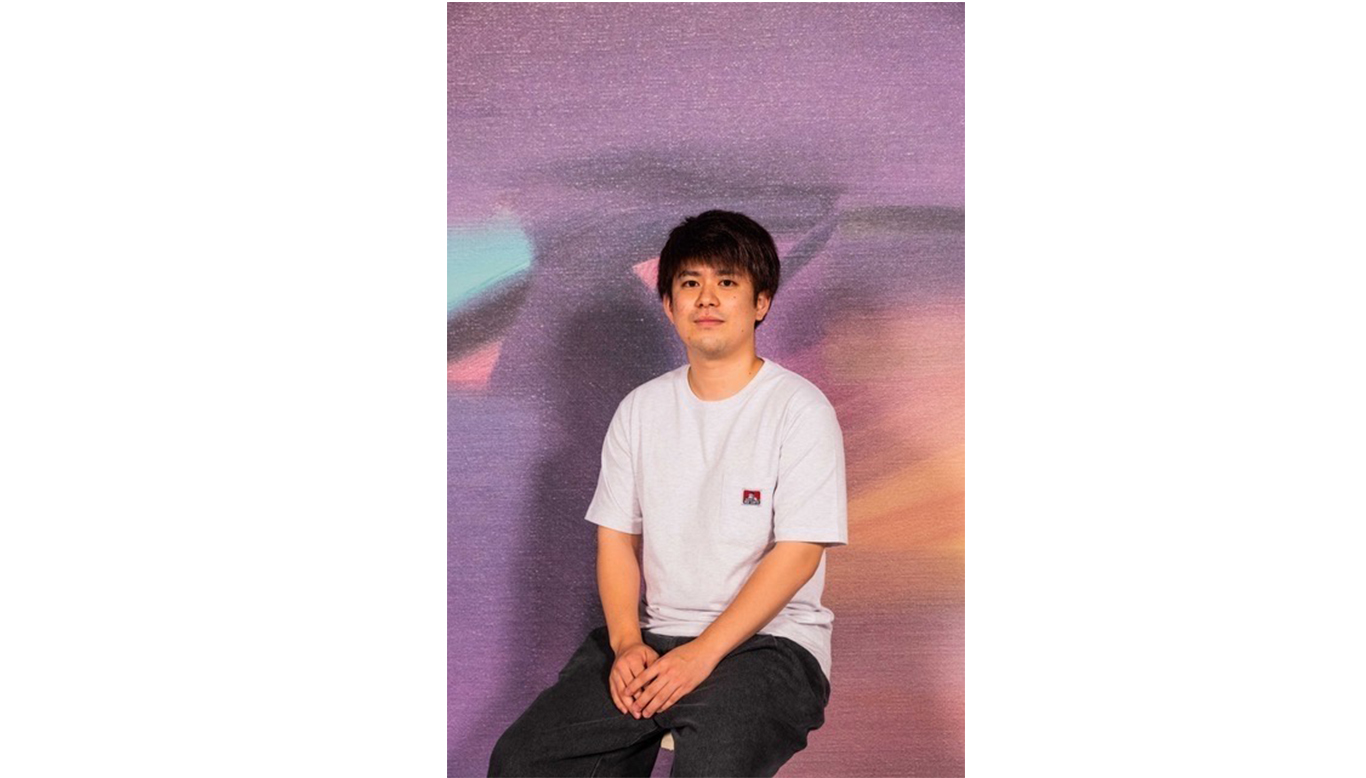
山田 康平 | Kohei YAMADA
1997 大阪府生まれ
2020 武蔵野美術大学油絵学科油絵専攻 卒業
2022 京都芸術大学修士課程美術工芸領域油画専攻 修了
個展
2022 「それを隠すように」biscuit gallery(東京)、「線の入り方」MtK Contemporary Art(京都)、京都岡崎蔦屋書店ギャラリースペース(京都)
2021 「road」代官山ヒルサイドテラスアネックスA(東京)
2020 「のぼり、おりる」ギャラリー美の舎(東京)
グループ展
2023 「Overlay」西武池袋展 (東京)
2022 「ぎこちない実感」 YODTOKYO (東京)
2022 「nine colors XVI」西武渋谷店(東京 )
2021 「biscuit gallery Opening Exhibition II」biscuit gallery(東京)、「Up_01」銀座蔦屋書店 GINZA ATRIUM(東京)
2020 「ARTISTS’ FAIR KYOTO」京都文化博物館別館(京都)
賞歴
2020 「CAF賞」入選



